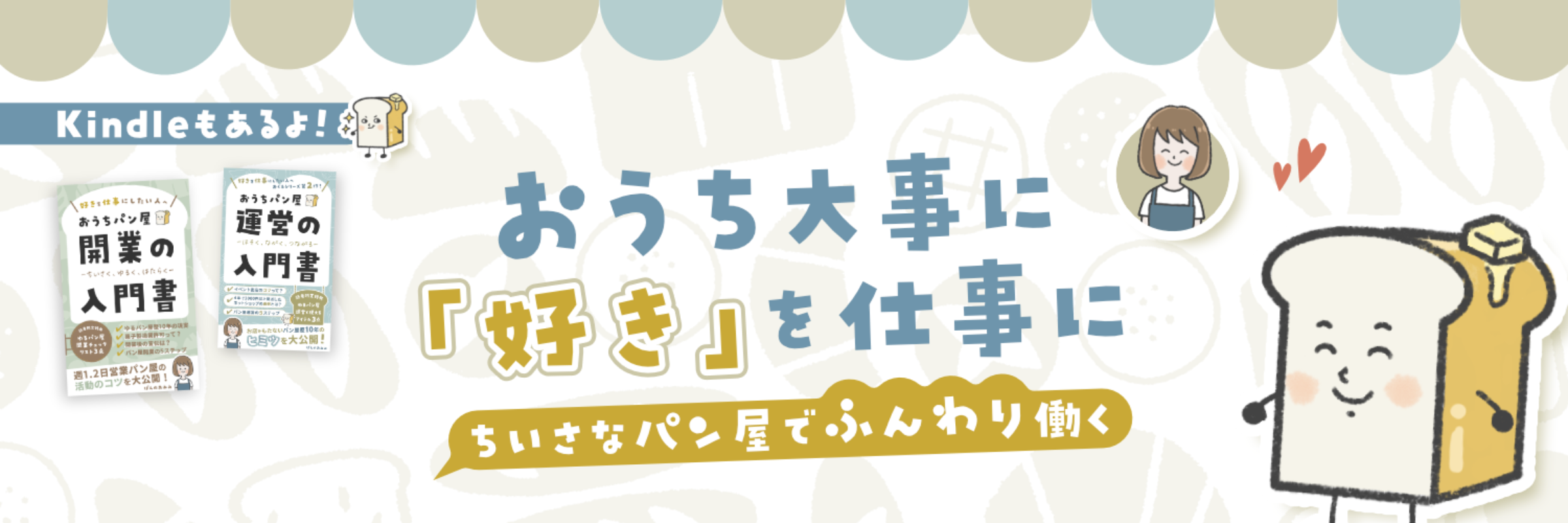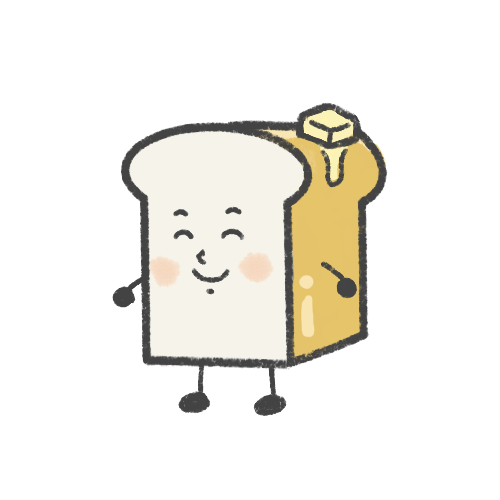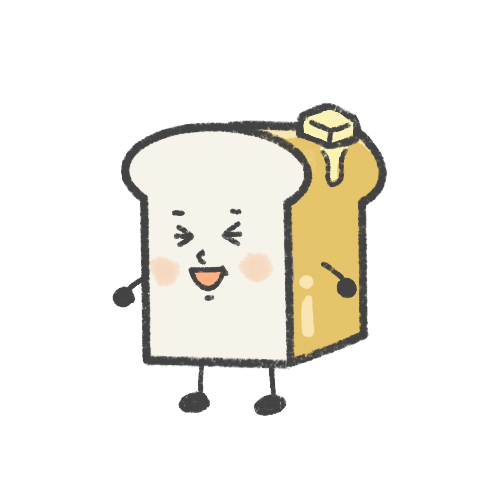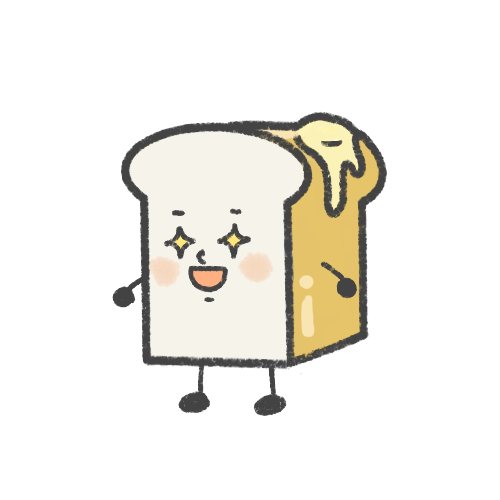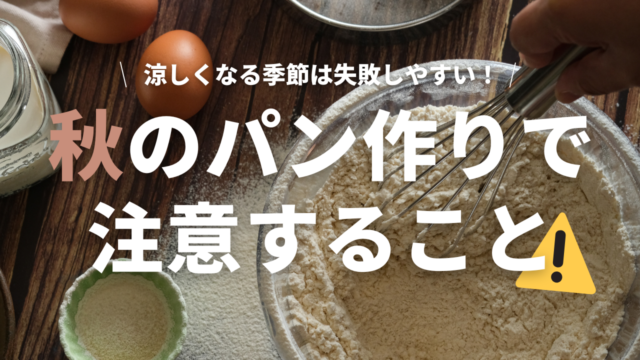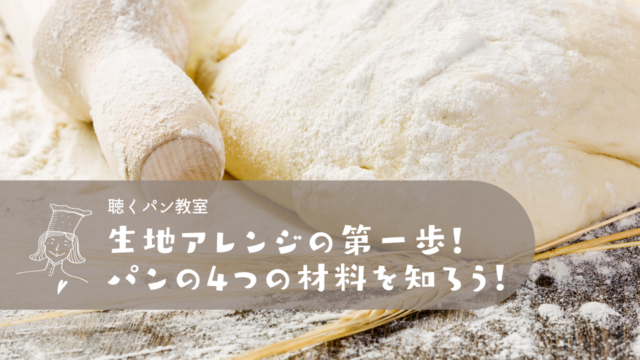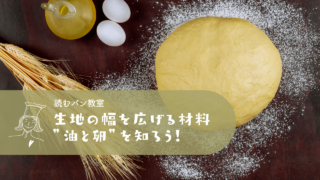今回は「パン生地の幅を広げる材料『砂糖』について」です。
補助となる材料「砂糖・油・卵」には生地の風味や食感をさらに変化させてくれる役割があります。
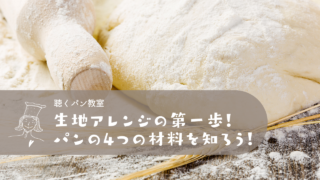
この記事は「砂糖」についてピックアップします。
イーストの選び方や配合のコツまでお伝えしていきます。
- 砂糖の役割と種類
- 砂糖とイーストの関係
- 配合のコツと生地への影響
砂糖はスーパーなどで手軽に手に入り、アレンジしやすい素材です。
いろいろ試しながら自分のお気に入りを見つけてみてね♪
砂糖の役割と種類

それではまず「砂糖」の役割をみていきましょう。
砂糖は「生地に甘みを加え、イーストの栄養源になる」という役割があります。
種類を変えることで甘みの度合いや焼き上がりの雰囲気も変わるのが砂糖の面白いところ。
また”保水性”があるので生地をしっとりさせて、硬くなりにくくしてくれるという側面もあります。
砂糖には固形と液体の2種類があり、水分やイーストの仕込みに影響してきます。
さまざまな種類がありますが、パンに使うものとしては「上白糖・グラニュー糖・きび糖・黒糖・はちみつやメープルシロップなどの液体の糖分」があります。

上白糖
上白糖はショ糖を主成分としたお砂糖です。
生地に使うとパンがしっとりして硬くなりにくくなります。
グラニュー糖よりも甘味がしっかりつきます。和食の多い日本では常備している家庭が多い印象です。
グラニュー糖
グラニュー糖は上白糖に比べてあっさりとした甘さとなります。
欧米には上白糖が存在しないらしく、一般的に砂糖といえばグラニュー糖を使用するそうです。
お菓子作りもグラニュー糖を使うイメージがありますよね。メロンパンの仕上げにも使用します。
きび糖
きび糖はミネラル分を残したお砂糖です。
上白糖やグラニュー糖に比べて”優しい甘さ”といったところでしょうか。
わたしはいつも”きび糖”を使用しています。生地が少しだけ茶色っぽく色づくのが特徴です。
黒糖
黒糖とはサトウキビのしぼり汁を煮詰めて作るお砂糖です。
きび糖よりもさらにコクが強くなります。
黒糖にしか出せない独特のまろやかさがあります。
個人的には沖縄に行くとご当地の黒糖を買うのが定番となっています。
きび糖よりもさらに茶色っぽい生地になります。
はちみつ
はちみつを砂糖の代わりに使用することも出来ます。
後ほど配合のコツで解説しますが、はちみつを使った生地は砂糖に比べて生地がかなりしっとりします。
そのため丸パンにすると生地がダレやすく、まんまるなパンにはなりにくい特徴があります。
セルクルなどの型に入れると形をキープして焼き上げることができます。
ちょうどいいサイズで言うと7センチ×4センチくらいのものを5.6個持っておくと便利です。
メープルシロップ
はちみつよりもサラッとしたメープルシロップ。
こちらも丸パンより型に入れた成型をお勧めします。
産地によって香りや色が変わります。
いろいろ試してみると良いでしょう。
砂糖はスーパーなどでもいろんな種類を手に入れられるため、生地のアレンジにはもってこいの材料です。
上白糖をきび糖に、きび糖をはちみつに。順番に挑戦してみよう!
砂糖とイーストの関係

砂糖をアレンジ素材として考えるときはイーストとの関係が重要になります。
イーストとは”生地を膨らませるため”の材料。
ここではインスタントドライイーストと砂糖の関係について掘り下げていきましょう。
使用するイーストはフランスの「サフ社」のドライイーストとなります。
”サフ社”のドライイーストには赤・金・青・緑の4種類があります。

赤は「砂糖の少ない生地に適したイースト」です。
糖分が10%くらいまでのサッパリした生地に向いていて、ビタミンCが添加されています。
※ビタミンC:グルテンを強化してくれる働きがあります。膨らみやすく扱いやすい生地になります。
金は「砂糖の多めの生地に適したイースト」です。基本的に10%以上の糖分が入った生地に使用します。
青は「赤とほぼ同じだけれど、ビタミンCが添加されていないイースト」です。膨らみの力としては赤ほどありませんが、落ち着いた生地を作ります。
緑は「ピザ用のイースト」です。本格的なクリスピータイプのピザに最適で、のびの良い生地を作れます。ナンを作るときにも使えます。
一般的によく使われるのは赤と金です。
イーストで仕込む場合、砂糖の量が増えたらイーストも専用のものを使うようにしましょう。
砂糖が多いのに赤サフ、砂糖が少ないのに金サフを使うと生地は十分に膨らまないよ!
配合のコツと生地への影響

固形の砂糖を使用する場合はイーストの種類に気をつけましょう。
赤は少なめの砂糖用の生地で使うイースト。砂糖が粉に対して10%以内まで使えます。
例えば粉を200g使うとして、砂糖が20gまでなら赤サフだね。
次ははちみつなど液体の糖分を使う場合。
例えば砂糖の代わりにはちみつを使ってシンプルなパンを焼くときは粘りがあるため、同じように入れると生地が緩くなります。
また固形の砂糖と同じ分量で入れるとはちみつの風味をあまり感じられません。
液体の糖分は香りが飛びやすいので風味として残すなら生地に対して20%は入れたいところ。
ただし糖分を多めに入れると今度はイーストの種類に影響してきます。
はちみつをたっぷり入れる生地には金サフを使おう!
生地の緩さの観点から見ると、はちみつは水分として考えた方が無難です。
はちみつを増やした分、水の量も減らしましょう。2つを合わせた量が仕込み水、と考えちゃいましょう。
混ぜ込むタイミングとしては水分と一緒に混ぜて大丈夫です。
粉類は粉類であらかじめ混ぜておき、水と一緒にはちみつを入れます。
冬ははちみつが固まるから湯煎しようね。
今回のまとめ

今回は「パンの生地のバリエーションを広げる”砂糖”」について解説しました。
- 砂糖の役割と種類
- 砂糖とイーストの関係
- 配合のコツと生地への影響
砂糖の量が増える時はイーストの種類を変える。
はちみつなどの液体で仕込む場合は金サフを使い、水分量は合わせた量を入れるようにする。
水とはちみつは合わせて仕込んでオッケー。こんな感じです。
次回は「第2部:パン生地の幅を広げる材料(油と卵)」について解説します。
油も種類がたくさん。卵は混ぜる量がポイント。それぞれコツがあります。
まずは今回の砂糖から挑戦してみてくださいね。